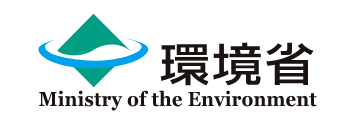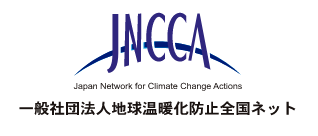サイドイベントの会場とCOPのメイン会場とをつなぐ通路の脇で、
ときどき、世界各地からのNGOたちのパフォーマンスが行われています。
前に紹介したI LOVE KPのTシャツを着た若者たちの
KP(京都議定書)を大事にしようという呼びかけであったり、
バイオマスの材料を名目とした森林破壊の阻止の呼びかけだったり、
GREEN CLIMATE FUND(グリーン気候基金)の設立に関する呼びかけなど様々です。

12月6日には、日本から来た学生グループCYJによる
「原発に頼らない温暖化対策」を呼びかけるパフォーマンスが行われていました。

たいていの場合、パフォーマーは若者たちです。
賛同者にシャツにメッセージを書いてもらうとか、
そうすると可愛い栞をもらえるとか、
なにかしらの工夫があって飽きさせません。
見ている人はそんなに多くはなにのですが、
たいていの場合、テレビなどのマスコミの取材がされるので、
それがパフォーマーたちの励みになっているようです。

会議の終盤の12月9日には、
会場入口付近でやや規模の大きなデモがありました。
最後まで見ていなかったで、いつ終わったのかわかりませんが、
マイクの持ち手を変えながら1時間以上は続いていました。
掲げるメッセージは「Honor KP」、「DON’T KILL AFRICA」、
「STAND STRONG AFRICA」など様々でしたが、
ここでも「I LOVE KP」のTシャツやロゴが目立っていました。

また、NGOからの参加者たちは、会議の傍聴席に座り、
自分たちの意見に賛同する発言には大きな拍手を送り、
そうでない場合にはブーイングするようです
(私自身はブーイングの場面には遭遇しませんでした)。
さて、このようなパフォーマンスやNGOの会議への参加は
どのような意味があるのでしょうか。
WWFジャパン気候変動プロジェクトリーダーの池原氏は、
二つの役割を掲げています(損保ジャパンホームページによる)。
ひとつは、海外のネットワークの仲間と連携して
「国益」でなく「地球益」が優先されるように働きかけを行うこと、
もうひとつは、国際交渉の現状を正しく伝えるということだそうです。
複雑極まりない会議内容について、
一般の報道機関担当者が長い年月に亘って
この問題を追い続けるのは現実的に困難であり、
この分野にあまり精通していない記者の方では
情報ソースが限定されてしまうので、
NGOの方が客観的な立場から状況を伝えることができるとしています。
また、12月11日のBBCのNEWSでは、
若者グループの存在やそのパフォーマンスが、
ともすれば行き詰りがちな、COPの会議にfreshness、
“Yes-we-can”-nessをもたらしたと述べています。
COPの会場にいて私が感じたのは、
会議の進行が冷徹な機械的なものではなく、
人間らしい感情も交えた生き生きとしたものだということです。
NGO、とりわけ若者グループの存在は、
会議の雰囲気に多少なりとも影響を与えたのだろうと思いました。
執筆:佐藤 剛
(宮城県地球温暖化防止活動推進センター ストップ温暖化センターみやぎ運営委員)