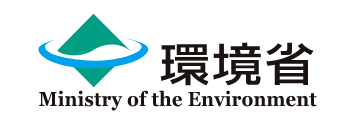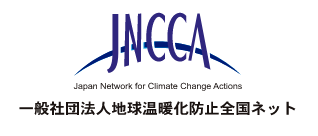カリキュラム概要
| 都道府県名 | 徳島県 |
|---|---|
| 設置区分 | 公立 |
| 学校名 | 鳴門市板東小学校 |
| 学校概要 | 鳴門市の南西部、大麻比古神社や四国霊場1・2番札所、第九交響曲アジア初演の地ゆかりのドイツ館など歴史的文化施設や,水田や蓮根田が広がる自然環境にも恵まれた地域。今年度創立150周年を迎える歴史のある学校。児童数238名 クラス数14 |
| これまでの取り組み | 本校では、学年の学習内容や取り組み状況に合わせて、県の環境学講座(出前授業)をお願いしている。例:4年生(ごみ問題) |
| 学年 | 6年生 |
| テーマ | 気候変動に挑む 脱炭素を目指して ~コウノトリと共に生きる板東 私たちにできること~ |
| 目標 | 気候変動問題と板東に飛来してきているコウノトリの現状が関連付いていることを理解することができる。コウノトリを大切に思い、適切に接することで、これからも板東にコウノトリが住み続けていくために、自分たちにできることは何かを考え、行動に起こせるようになる。 |
| 内容 | 1学期は地球温暖化とコウノトリについて知り、自分たちもコウノトリに親しみをもつため、見つけたら発見カードに書いていった。また、化学肥料や農薬を減らした米作りを知る一貫として、田植えを体験した。さらに、農地などの雨水貯留の効果についても学んだ。JICAとも連携し、スリランカの環境問題について知った。2学期は田植えをしたお米の稲刈り体験と地産地消での調理実習を行った。スリランカと2回目の交流を行い、互いに環境問題について意見交換ができた。これらの経験から、自分たちにできることは何か4つの視点から考え、発表していく。 |
| 大切にしたこと | 難しいテーマに取り組んだので、最初はたくさんの外部ゲストをお呼びして、具体的に話をしてもらうことで、より分かりやすく、児童にとって身近な問題であるということを意識づけるようにした。また、インプットだけで終わるのではなく、自分事として捉えアウトプットできるように、エコみらいとくしまの皆さんの力を借りながら、自分たちにできることを考えていった。子どもたちは4つのテーマに分かれ、それぞれのテーマの視点でできることをしっかりと考えられるようになった。学校だけでは難しいことも、外部の専門的な力をお借りすることで、児童の意欲の向上や、解決策が見えてくると感じた。 |
| 外部協力者 | エコみらいとくしま 認定NPO法人徳島コウノトリ基金 松浦酒造 志まや味噌 ビオトープ米農家谷口様 徳島大学 河口様 スリランカ派遣 南様 とくしまCSA風土金村様 |
フォトギャラリー





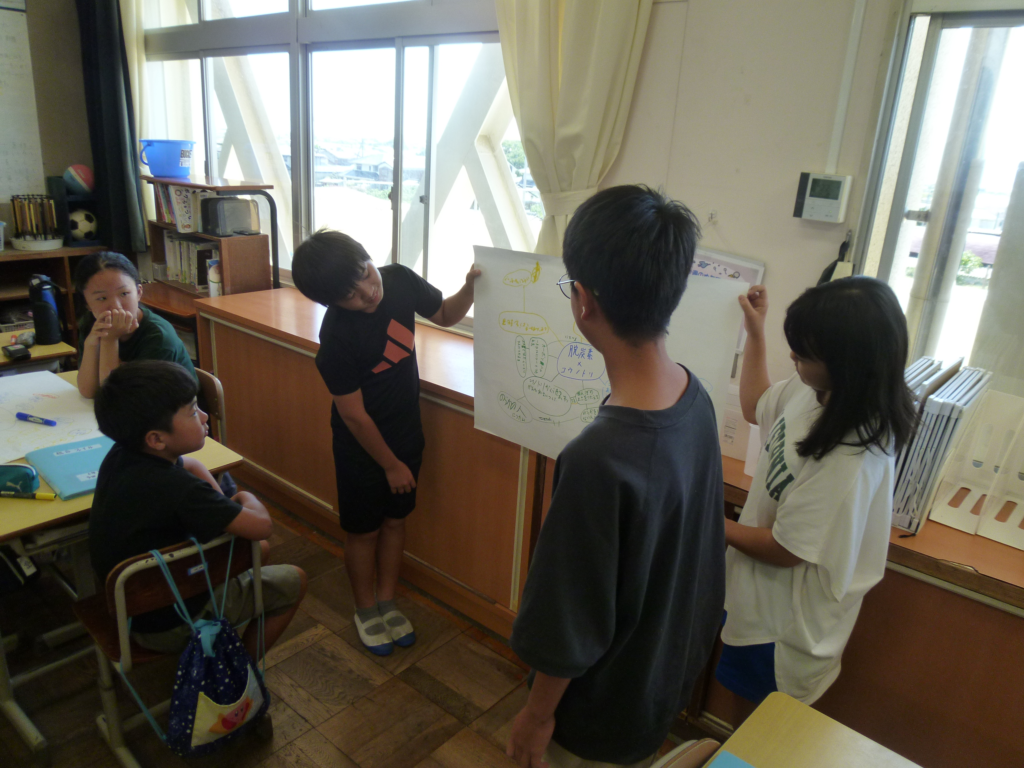
取り組み
令和6年5月~令和7年3月
1学期
「地球温暖化・コウノトリ・農業の取組について知る」(13時間)
○5月14日:エコみらいとくしま、コウノトリ基金による出前授業 2時間
・コウノトリの生態について知る・地球温暖化について知る
○5月:コウノトリ発見カードの配布…放課後や登下校時、休日にコウノトリを見つけたら記録する
○6月18日:田植え体験(ビオトープ米でお酒を造るプロジェクトの取組を知る)4時間
松浦酒造、ビオトープ米農家、コウノトリ基金
○6月21日:農地の多面的機能についての出前授業(徳島大学:河口先生)1時間
○6月25日:コウノトリの絵作成 2時間
○7月5日:スリランカとの交流(JICAオンライン出前講座:南優香 先生)4時間
スリランカの文化や環境問題について知る。質問コーナーなど
○夏休み中の課題:「脱炭素×農業」について他県の取組や徳島県の取組について調べる。
2学期
「自分たちにできることを考え、発表する」(22時間)
○夏休みの課題「脱炭素×農業」について調べてきたことを発表する。 3時間
○「みどりの食料システム戦略」について知る。(エコみらいとくしま布川さんより)2時間
○10月2日:稲刈り体験(ビオトープ米でお米を造るプロジェクトについて知る)3時間
松浦酒造、ビオトープ米農家、コウノトリ基金
○10月29日:調理実習(CSA風土金村さんコウノトリ基金)3時間
収穫した米でおにぎりと、鳴門産わかめ、収穫した米でつくった味噌、鳴門産蓮根、鳴門金時を具材とした味噌汁を作る。地産地消と食品ロスの話を聞く。
○11月12月:振り返りとまとめ
これまでの学習から、コウノトリと共に生きていく私たちにできることを考える。
方法:グループ討議、ワールドカフェ、タブレットを用いての調べ学習など
「食料システム戦略」の4つの課程で、脱炭素とコウノトリが暮らしやすい地域づくりの点から例をいくつか掲示する。
○1月:スリランカとの交流②
子どもたち同士の交流(6年生同士)学校紹介や地域の紹介、環境問題についてお互いに学んできたことを伝え合う。クイズや質問タイムなど。
○1月2月:まとめ
これまで学習してきたことから、4つの観点に絞りそれぞれのグループで自分たちにできることを考える。
○1月31日:徳島環境学習フォーラムでの発表
○2月16日:板東小学校創立150周年記念式典での発表
児童の変化
<児童・生徒の変化について>
始めは受け身だった児童たちもコウノトリの観察等を通して、コウノトリに親しみをもち、自分たちも温暖化を防ぎ、コウノトリを守ろうという気持ちが高まってきた。出前授業や体験活動を豊富に取り入れたことにより、子どもたちの気持ちが途切れることなく継続して課題に取り組めてきた。それにより、後半の自分たちにできることも色々なアイディアを出し、主体的に取り組む児童が多かった。
<児童・生徒の変化をどのようにして評価したのか>(アンケート等)
・各出前授業後に書いた感想文から、児童の変化をみとる。・グループ活動での様子。自分事として考えたりアイデアを出したりして主体的に取り組めているか。
参考資料(詳細な年間スケジュール等)
令和6年度総合的な学習の時間年間指導計画
鳴門市板東小学校12月5日学習指導案